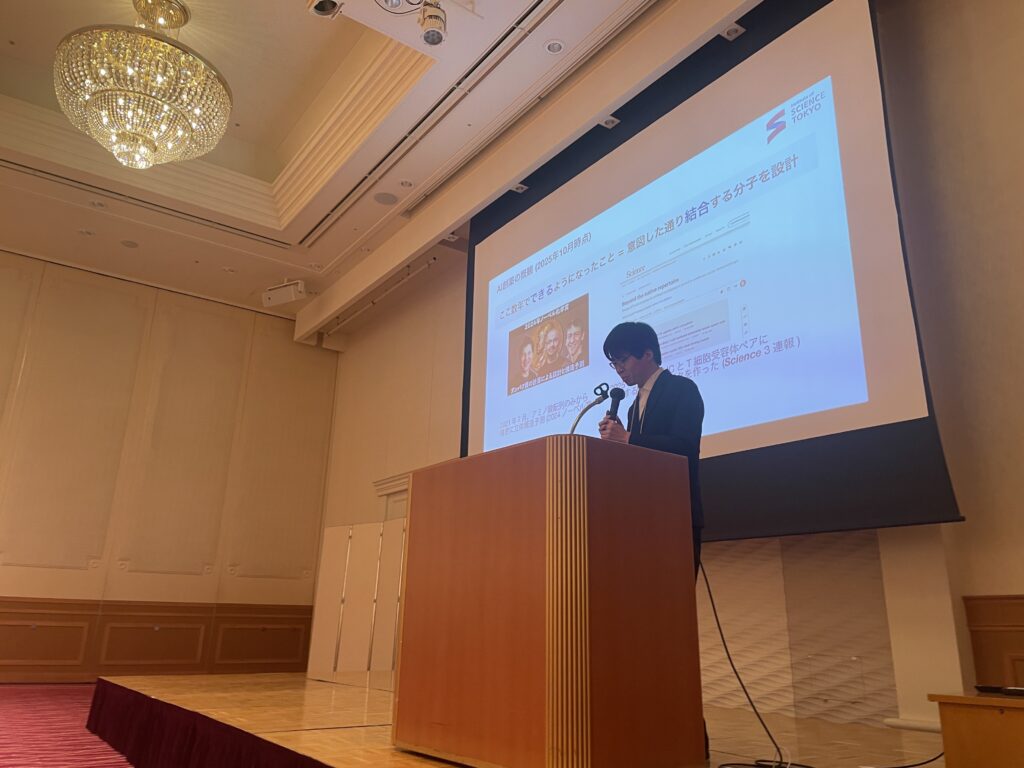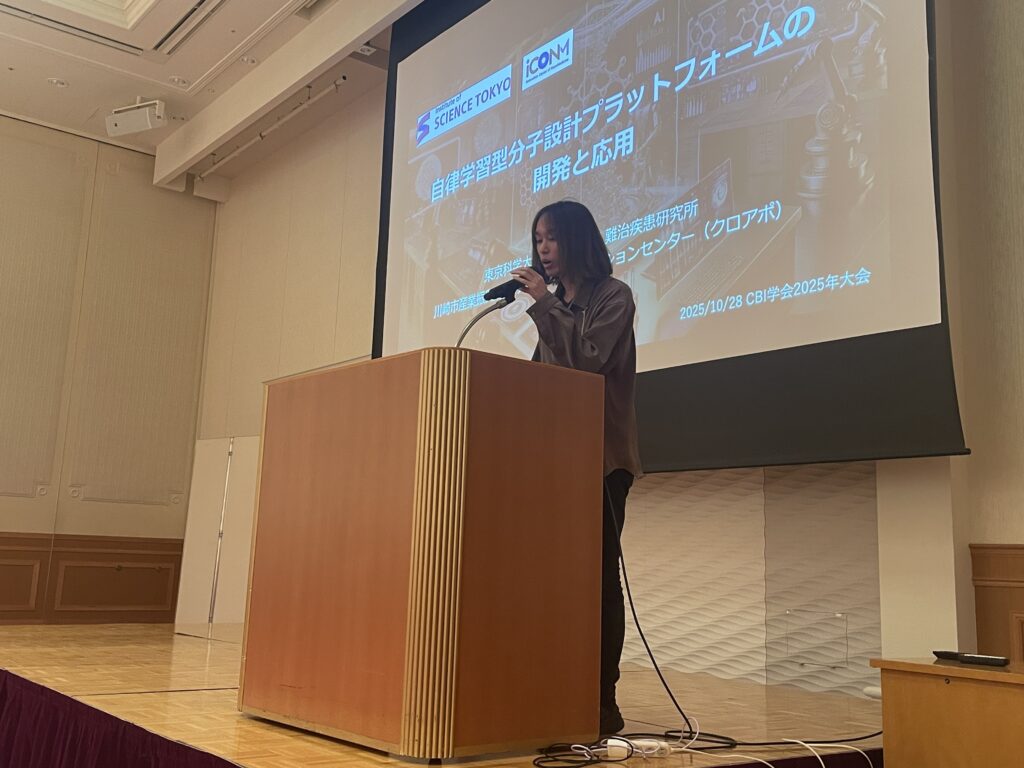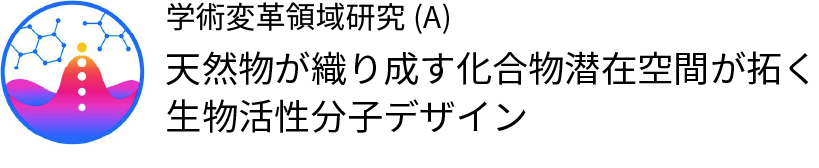CBI学会2025年大会で共催セッションを開催しました!
2025年10月27日から30日に行われたCBI学会2025年大会にて、本領域のセッションを開催しました。
SS03 スポンサードセッション https://cbi-society.org/taikai/taikai25/sessionSS.html#SS03
学術変革領域研究(A)天然物が織り成す化合物潜在空間が拓く生物活性分子デザイン
日時:2025年10月28日(火) 14:00〜15:30
会場:タワーホール船堀 2F 福寿
モデレーター(座長):鎌田 真由美(北里大学)、大上 雅史(東京科学大学)
プログラム
SS03-01 榊原 康文(北里大学)「タンパク質特異的な化合物生成モデルの構築とタンキラーゼ阻害剤への応用」
SS03-02 岩田 浩明(鳥取大学)「AIによる医薬品候補化合物評価モデルの開発と共同研究での検証検討」
SS03-03 清水 秀幸(東京科学大学)「抗菌活性を題材としたAI駆動型の天然物マイニングと中分子デザイン」
SS03-04 林 周斗(東京科学大学)「自律学習型分子設計プラットフォームの開発と応用」
CBI学会は、化学(Chemistry)、生物学(Biology)、情報計算学(Informatics)という3つの学問分野に関わる先端的な研究開発の基盤構築をめざす学会で、製薬企業や創薬支援企業の参加者・出展が多いことも特徴です。本領域も親和性が高い学問分野の学会であり、4日間に渡って行われた2025年大会の中で本領域との共催セッションを開催させて頂きました。プログラムは本領域の情報解析班の研究成果を中心に構成しました。冒頭に、大上雅史先生より領域の概要とセッションの趣旨についてご説明いただき、続いて各登壇者による講演が行われました。
最初に、計画研究班であり情報解析班長の榊原康文先生(北里大学)から「タンパク質特異的な化合物生成モデルの構築とタンキラーゼ阻害剤への応用」と題してご講演をいただきました。領域の中心概念である「潜在空間」の概要と、その出発点となった分子生成AI「NP-VAE」についてご紹介いただきました。また、その発展形として、Transformerを導入したFLATTVAEモデルの開発や、タンパク質言語モデルの統合により標的タンパク質情報を条件とした分子生成を実現したFLATTPROモデルを紹介され、これらの成果を実験系グループ(A/C班)と連携して展開していることをご報告いただきました。
続いて、第1期公募班から3名の先生にご登壇いただきました。まず、岩田浩明先生(鳥取大学)より「AIによる医薬品候補化合物評価モデルの開発と共同研究での検証検討」と題し、マルチタスク学習を用いた標的タンパク質予測AIやADME予測AIの実例をご紹介いただきました。
次に、清水秀幸先生(東京科学大学)からは「抗菌活性を題材としたAI駆動型の天然物マイニングと中分子デザイン」として、抗菌活性予測AIの開発と、予測された複数の候補物質が実験的にも狙った抗菌活性を示した事例をご紹介いただきました。
最後に、林周斗先生(東京科学大学)より「自律学習型分子設計プラットフォームの開発と応用」と題して、AI駆動型分子設計における設計・評価を循環的に行うプラットフォームの構築や、ベイズ最適化と生成AIを組み合わせたタンパク質設計など、最新の取り組みをご紹介いただきました。
当日は多数のセッションが並行して行われている中、多くの方にご参加いただき、AI・情報科学による創薬研究の最前線を共有する貴重な機会となりました。ご登壇くださった先生方、ご参加の皆様、運営にご尽力くださった関係者の皆様に、心より感謝申し上げます。